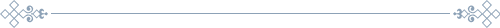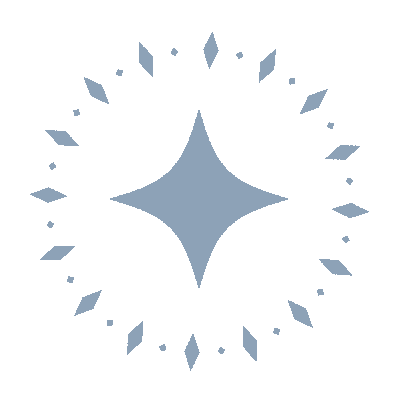雪夜のロンド
星を埋めても花は咲かない
それは金の目。月のような、星でもあるような目。
白の髪をなびかせて影はこちらを見つめている。
向けられるその目を、シュネルがまず感じたことは「どこかで見たことがある気がする」だった。
はてさて、それは誰のものだったか、と考える前にユーリヤは言葉で遮った。
「君は? それに楔の星って」
さあさあ。緩やかな風が何処からかなびいている。風と共に花も揺らぐ。
問われた影はその金の瞳を細めては言うのだろう。
「星の災害。それは全宇宙に及ぼす概念、災い」
「君達はそれを止めるべく楔の星として、この楽園へと招かれたんだよ」
「僕はその楽園の管理者……星穹の調停者」
星の災害、楽園、星穹の調停者。
その言葉にシュネルはぐるぐると頭を巡らせる。それを理解するにはあまりにも急すぎて。
それは、他の者も同じようだった。少しだけの刹那、静寂が続く。
さあさあ。風と共に花も揺らぐ。
ひらひら。花と共に魔力の蝶が舞う。
きらり、きらり。星が瞬きそれを湖が鏡のように映している。
最初に静寂を破ったのは、星詠だった。
「私達がその災害というのを止めればいいのかな? ……全宇宙にまで及ぼすものをたった5人だけって無茶すぎないかい」
「それもそうだ。勝手に呼んでおいて災害を止めろだなんてな」
それに続くようにユグドラシルも文句を垂れた。
2人が言葉を紡いでもまだ、シュネルは事の大きさを理解できずにいた。
全宇宙だと、どれくらいの規模なのだろう。
未だに理解が出来ぬまま、話は進められていく。花は呼応するように揺らいでいく。
「君達5人だけではないよ。月蝶、天理……他の調停者や観測者もいる」
「それでも規模のわりには少ないないかい?」
「……君達しかいなかったんだ。星の災害を止められる力を持つ者達が」
きらり、きらり。その星の瞬きは星穹の調停者と呼んだ影を示している。
星の光がよく似合うものだ、と誰かは思ったことだろう。
「ええと、君の名前を教えてもらってもいい?」
「ルメラリア。ルメラリア・ルーティファウルと言うよ」
ユーリヤの言葉に、ルメラリアという名を影は返した。
この楽園に呼ばれた理由は理解出来た。
湖に映されている瞬きと呼応する花々がやけに綺麗に見えた気がした。
他の者はともかく、シュネルは自分にそんな力があるとは思えない。
本人も、本人以外も、ルメラリア以外の誰もが思ったことだ。
「楔の星……特にユーリヤと星詠、シュネルには力が宿っている」
「僕はこれを楔力を呼ぶ」
「本来成り得ないものになる力。もうひとつの結末。それが楔力」
本来成り得ないもの。
ルメラリアは確かにそう言ったのだ。
それに対してはシュネルは心当たりがないわけではなかった。
星導の瞳。確かにこの授かった力を使えば自分は人ではなくなると聞いた。
成り得ないものとは、きっとそれのことだろうとシュネルは理解をしたのだ。
ユーリヤも、あの時あの場所で見た、別の世界の自分のことだろうと、思ったのだ。
対して、星詠は成り得ないものというものにあまり腑に落ちないい様子だった。
シュネルのように授かったわけでも、ユーリヤのように別の世界の自分を見たわけでもない。
「いずれ、それは理解できるものだよ。その時はいずれ来るのだから」
それだけ言うとルメラリアは、ふ、と姿を消した。人の気持ちなんて知りもしないで。
残された者達は互いを見やる。
「……なんだかとんでもないことになってしまったね」
ユーリヤが静寂を破る。それには他の者も思ったことだろう。
星の災害。楔の星。楔力。
結局靄はかかったまま、ルメラリアは行ってしまった。
「私達だけで星の災害を止めるという話になるとはな……」
「ま、なんとかなるだろうよ! 今までだってなんとかしてきた子ばかりだろう!」
「それも……そうかもしれませんね!」
オルレウスの言葉に、星詠の様子。そして、星詠に賛同するシュネル。
それが一層にユーリヤとユグドラシルを、大丈夫かなぁ……と心の内をさせたのだ。
不安を主に、その場にいた者達もやがては場を去ったのであった。
いつ起こるのかわからない星の災害。
そのカウントダウンは、もう始まっているのだ。