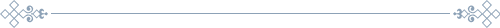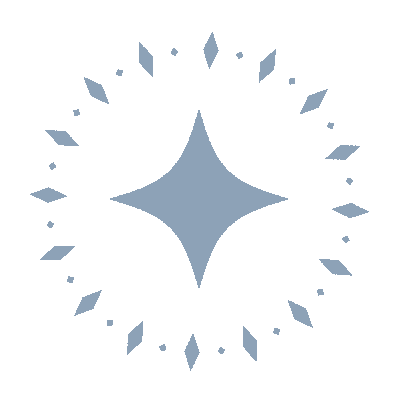雪夜のロンド
星が沈めば治るでしょう
楽園にも、朝は来る。
しかし、景色はいくら視界を瞬きしても星空からは変わらない。
今日も、シュネルは楽園にて目覚める。
扉を開けると、ふんわり、いい香りがする。ユーリヤが朝ごはんを作っているのだろう。
とん、とん、とリズムを刻むと香りも頬をくすぐる。
賑やかな声が聞こえてきたのなら、扉に触れ音を立てた。
「やあ、おはよう。お邪魔しているよ」
まず聞こえてきたのは、他の四人でもない声。そして視界に入るは白髪の男性であった。
ふにゃりと笑うひらひらと手を振るそのひとは、きらきらとまばゆく星を思い浮かばさせるひとであった。
シュネルは、おはようという言葉に返すと、訳も分からず席に座り、そのひとを見る。
綺麗なひとだ、とシュネルは思った。
男性は、シュネルをじ、と見つめると、にっこりと笑んだ。
「私はイドアと言うんだ。イドア・イステア」
「ルメラリアから話は聞いているよ。楔の星なんだって」
はくり、と焼けた香りのするトーストをかじりつつイドアは言う。
さも当然ようにここで朝ごはんを食べている。そんなイドアに誰もが困惑していることだろう。
トーストを食べたイドア頷き、満足そうな表情。
一体何の用だ? 皆がそう思った刹那、イドアは、あっと声をあげた。
「そうだ、みんな僕のこと何しに来たんだ、って思ったところだろう」
「うん、うん。特に何もない」
気の抜けた声、言葉。一人か二人くらいはツッコミたくもなる。
更に部屋の奥から「何もないんだ……」というユーリヤの声が聞こえる。
呆気にとられて、ついシュネルもほわぁ……なんて声が出てしまった。
「そうなんだよね。ルメラリアみたいに重要な話があるわけでもないし。そういう話はあの子が全部しちゃってるからね」
かちゃり、ユーリヤがおかずの皿をテーブルに並べる。
それを眺めてイドアは目を細めてなんだか楽しそう。
用がない。だがそれだけで来ては悪いのか、と言う者なのだ、イドアという者は。
皿をシュネルの前にまで置き終わると、ユーリヤもかたんと席につく。
イドアは、ユーリヤの隣だったようで、ユーリヤの方にもにっこりと笑む。
それに釣られてユーリヤもまた、笑むのであった。
かたこと、かたり。
しばらくは食器の音が宴を奏でる。
ユーリヤはイドアの分も用意していたようで、その宴にはイドアもいた。
イドアは、ゆっくりと、食を進める。その間に誰か一人食べ終わってしまいそうなほどに。
まず最初に、食を終えたのは星詠だった。イドアを見るとからかうように言葉を紡ぐ。
「おや、随分とゆっくりだね。もしかして、ご飯を食べるのに慣れてない?」
まるで彼が人ではないような言い方。しかしイドアは星詠の言葉にうん、と頷く。
頷いたイドアを見て、ユーリヤとシュネルは少しばかり驚いた。
「人の食事というものは、案外大変だね。顎……が疲れてしまうね、結構」
「そうなんだよね~、これを一日に三回もやっているだなんて、まいってしまうよ!」
その会話にシュネルが入ることは不可能に近かった。
星詠がまるで、そんな人ではないようなことを言うだなんて。なんて思ってみたりもして。
まだ、星詠のことを知るには時が浅すぎたのだ。
星詠だけではなく、ユグドラシルとオルレウスだって、そうなのだ。
彼らのことは、この楽園で出会ったばかり。
一体どれだけ、彼らと時を紡ぐのだろうか。
シュネルは、この日々の終わりを考えて、少しだけ胸に空白をあけた。
そして皆が食事を終えた頃、シュネルはイドアに言の葉を歩んだ。
「イドア様、今日はもうお帰りになられるんですか?」
「うん、用事もないしね」
本当にになかったんだ……とその言葉を聞いてシュネルは思う。きっと皆もそう思うであろう。
だけど本当にすぐ行ってしまうのは、案外寂しいものなのだ。
シュネルがもう少しだけいませんか、と言うと、イドアは刹那の間だけ考えてはシュネルの言葉に頷いた。
このまま帰ってしまうのも、なんだしね。と、言ってからイドアはシュネルと共に部屋に戻り、近くにいた星詠と言葉を交わすのだ。
賑やかな部屋、声が交わる空間。まるで星の災害なんてものは起きないようで。
このままなんでもないような一瞬が続けばいいのにと、胸の内で願う。
一体どれだけの平穏が、時を刻むのだろう。一体どれだけの安らぎが、時を刻むのだろう。
時は過ぎ、時刻は夕方を指していた。時計はもはやカチカチと数字を指すものだけに過ぎないものではあるが。
「それじゃあ、楽しかったよ。星の災害の時にはよろしくね」
「簡単に言うな~」
ひらり。イドアは手を振ってからシュネル達の前から消え、去っていった。
各々が部屋に戻り、身支度も済ませた頃。
かたり。シュネルは窓を開け星躔の空を眺めていた。
もし本当に星の災害が起きるようでは、この平穏も続くことはないだろう。
またもやシュネルは頭の中をぐるぐると駆け巡らせる。
落ち着かせるために、深呼吸をする。大丈夫、自分にはユーリヤ達がいるのだと。
シュネルの胸の内なんて知らずに空は瞬く。
いつもは青白い星の光がなんだか赤く見えたことは、シュネルはまだ知らなかったのだ。
時は、巡る。星も、巡る。