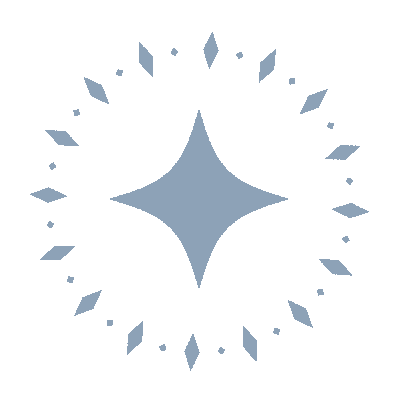雪夜のロンド
さよなら、私の愛した世界
人によっては、今宵の星はきらり、きらりと瞬いているのだろうか。それともはぴかぴかと光っているのだろうか。
星詠にとっては、どちらでもない。星は、まるで人々に呼びかけるようにきらめいているのだ。
星はいつだってそうだ。誰よりも、何よりも近くに世界というものにいる。きらめきの星光を見上げ、星詠は思う。
だけど、星は人に忘れられる。例え賛美をされていたとしてもそれはひとときの間。星光が見えなくなったら皆、忘れてしまうものだ。
だからだろうか。星というものに親近感というものを感じるのは。かつての栄光。古の世界。遥か遠くの記憶。それらを廻るように思い起こす。それらも、全て忘れ去られてしまった過去の話だ。
皇神ユーディオン。それがかつての彼の名前。
彼は確かに神々の中の王であった。宇宙を統べるほどの神であった。だが、それもすぐには。
そこで星詠を思いを廻らせるのをやめた。もう過去のことだ、過ぎたことを思い返してもしょうがない。
確かにあの時、自分は若き神である“ゼウス”の名を持つ神が築き上げる世界を見届けた。自分の築き上げた世界は終焉を迎えたのだと、知った。
今の自分は、宇宙ですら統べることができる皇神ではなく、ただ1人の男“星詠”なのだ。
もうすぐ夜が明ける。辺りが暁から黎明へと変わりゆく。もう星々は過ぎ去っていくのだろう。
いや、姿かたちは見えなくても星々たちはいつだってそばにいる。だから。
星詠はきらめく星光が薄まっていき、陽の光が登り始める景色を見る。
星々たちはいつだって傍にいる。
だから、寂しくなどはない。悲しくもない。星光のきらめきがある限り、彼はきっと前を向いていけるのだろう。
──さよなら、私の愛した世界。
それは、夜明けと共に