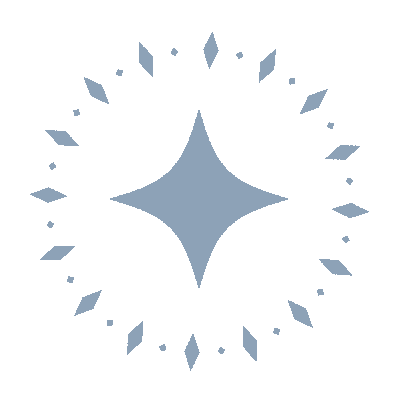星楔のヴァリアシオン
青にくわれた残滓
あと何回この呼吸は繰り返すことが出来るのだろう、あと何回この世界の朝を迎えることが出来るのだろう。
もはや棺のようにも見えるベッドに横たわるたったひとりの家族の姿。
それを記憶に焼き付けては、エルロスは今日もこの交わることのない世界たちの中で息をする。
世界を歩くこのかすかな音でさえも、今の自分には憎いものとなってしまっていて。
数年前の時のことだ。エルロスの家族が、“幻獣種”に殺され、残ったひとりはもうからだも動かなくなってしまったのは。
エルロスは、家族の最期の姿を見てやることはできなかった。結局、それがよかったのかもエルロスにはわからない。
しかし、妹が今も苦しみながら生きていることだけは、確かだ。
一度、幻獣種の中で王と呼ばれているオルティレイス、に会ったことがある。
もちろん怒りもぶつけたものだった、「お前らのせいで不幸にならずにすんだ人が何人いると思っている」……と。
オルティレイスは、ただその言葉に、怒りを見せるわけでもなく。ただその言葉に悲しみを見せるわけでもなく。
ただ、オルティレイス──幻獣種の王はこう言ったのだ。
「俺はお前らが死んでもくたばりはしない」
「だから、殺す気で恨め、憎め」
「──お前らの憎悪をぶつける先は、この俺だ」
その蒼いひとみにはどんな感情を宿していたかはエルロスにはわからない。
それでも、エルロスの感情を同じものを宿してはいなかったことだけは、それだけはわかる。
煮えたぎるような、感覚を体に走らせてはエルロスは考えることをやめる、幻獣種のことになるといつもこうだ。
エルロスだって、考えないことは、なかったかもしれない。
幻獣種と人間が当たり前のようにこの世界で、似たようなふたつの青の真ん中で笑い合っている、だなんて。
けれどそれはもう、エルロスの中では海の中で消える泡のような話だ。
復讐だなんて死んだ人は悲しまないだなんて誰が決めた?
復讐だなんて悲しみが連鎖するだなんて誰が決めた?
そんなの、上等じゃないか!悪者は向こうだ、幻獣種だ。その、はずだった。はずだったのだ。
「……幻獣種。もし、お前らは家族を殺されたら、殺したそいつを赦せるのか」
とある幻獣種に投げた問いだ。赦せないか、赦せるかのいたって簡単な問いだ。
そう、目の前の彼は真っすぐと、海のような蒼をエルロスに向けたまま。
「そいつがとことん苦しんでくれるなら、赦してやってもいいかな」
……ああ、そうか。エルロスはすこし、笑みをえがく。
その言葉に、ちょっとは救われたような気がして。
同時に、あふれる、伝う、そしてひとつぶ落ちる温もり。
ああ、なんで自分は。幻獣種なんかの言葉にこんなにも胸のざわめきを取り除いてしまったのだろうか。
この世界。ふたつの青が交わることのないこの世界は、少しずつ幻獣種というものをゆるそうとしている。
そうか。そうか。きっとゆるさなくたって、いいんだ。
その結果がどんなに苦しいものとなろうとも、エルロスはこの選択肢を選ぶのだろう。
エルロスが持つ人生の旅路というものは、憎むべきに在るべきだと。
いつのまにやら止めてた音を、またカツカツと。その瞳には、迷いはなくなっていた、だなんて。
青にくわれたひとつの残滓。それがまた元のようにやさしくなれるなんことは、たぶんきっと。もうないことなのだろう。
だけれど、前よりは少し、こころというものが救われているものだった。