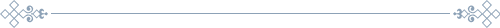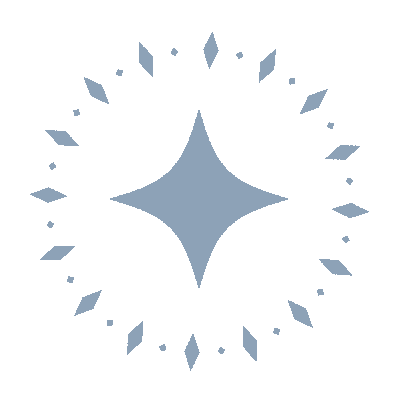Amartya tis Theos
戦いよ、幕を開ける時だ
炎、炎、炎。
焦がすような熱が音を立てて揺らめている。
立ち尽くすミラは逃げもせずにその赤い熱を眺めていた。
どうしてこうなったのか。ああそうか、戦争か、これが戦争というものなのか。
熱の中を歩む、歩む。焼けるような痛みなど気に留めず、歩む。
炎しかない世界はまるで終焉の黄昏を迎えているようだ、とミラは思ったことだろう。
「……やり直さなきゃ、全部、最初から、」
その声はもうあの人達に届くことはない。
そうだとしても、少女は願うのだ。
あの人達が生きている世界を──。
太陽の光が眩い朝。ミラは深い夢から目覚める。
なんだか嫌な夢を見ていた気がする、と思うがそれはもう記憶には思い起こされないものだ。
シーツの海からゆったり、硬い床に足を降ろす。
床は冷たい。何故だか今はそれにどうしようもなく安堵してしまう。
今、この世界では戦争が行われようとしている。
オーディン。その神がアマルティアという戦争を引き起こそうとしている。
それを知らされた日から、ミラはあまりよく眠れていないもので。
まさか、あの大樹がもうひとつの世界だっただなんて、神ですらも予想がつかなかったであろう。
戦争。その文字が脳裏をやたらと羅列させるのだ。
ネックレスを握る。このネックレスは物心ついた時から身につけていたもの。
このネックレスを握っているとなんだか安心を覚えるもので。
そうしていると、段々と穏やかではない心も落ち着き、深呼吸。
窓を開けると視界に青。穏やかなひとときも今日が最後か、それとも明日なのかもわからない。
晴天の空、雲はゆったりと進んでいく。鳥も自由を謳歌するように飛び立ってたりなんかして。
風が、時を進めていく。
やけに静かに感じるような空に背け、ミラは部屋を見やる。
この部屋ともしばらくはお別れだ。片付けられた空間、それが寂しさを増した。
そうして荷物を持ち、扉を開いた。響く音が別れを告げているよう。
外に出ると、ゼウスがミラを迎える。
ミラは、ミラだけはゼウスの元に引き取られることになったのだ。
「ミラ、おはよう。準備は出来たかい?」
「はい、ゼウス様。……ちょっと、寂しいですけれど」
言葉を聞くと、ゼウスは微笑む。その笑みは穏やかなものだ。
ゼウスとは小さい頃からの付き合いらしいとミラは聞いてた。もっとも、ミラにはその記憶はないのだが。
しかし、笑みを見ているとなんだが安堵を覚えるものだった。
時折、もし兄がいたらこんな感じだっただろうか?と思うことも。
二人は歩む。なんて穏やかな日なのだろう。ミラは思う。
戦争が起きるなんて、嘘なんじゃないか。しかしそれを言葉に出す勇気はなくて。
その刹那のことであった。二人の前に、影。
「アンタがゼウスと……誰? まぁいいや。今日はわざわざこのボクが挨拶に来てやったよ」
金色の髪。それがなんだか炎を追想させる。その影は、少年のように見えた。
ぱちん。少年が指を鳴らす。
一番先に感じ取ったのは、熱。視界が赤に染まっていく。
漕がれるような熱と赤。まるで、これを前にも感じていた、ような。
ゼウスは槍を出す。その槍で炎を薙ぎ払い、体勢を取る。
バチバチと槍は雷を纏い、炎を消し去っていった。
少年は、くく、と鳴らしては楽しげに。
「アハハ! 安心してよ、主神様とまともにやり合おうなんて考えてないからさ!」
「……ッ! ミラ!」
熱が、炎の渦がミラを取り巻こうと、していた。
ミラが身につけていたネックレスを握った、瞬間のことであった。
弾ける炎、冷めていった熱。ネックレスが光り、炎からミラを守ったのだ。
ぱちり。ミラはその出来事に瞬きをする。驚いたような顔をさせるゼウスと金髪の少年もいたもので。
次に、少年は面白いと言わんばかりに、嗤ってみせた。声がこだまする。
ネックレスは、もう誰の声にも応えることはなかった。
「へぇ、ただの人間かと思っていたけど、そうでもないんだね。随分と神様に愛されたようで」
その言葉にはよくわからないでいるミラ。なんのことやら、と思っているうちに少年はゼウスに言う。
「ボクはロキ。アンタ達と戦うことになる世界樹ユグドラシルの、北欧の神さ」
「……君が、あの大樹の」
ゼウスは、槍を離さずにいる。ロキを視界に入れたまま、ミラを守るように二人の間に入る。
それだけ、なんてロキは言うとロキの周りに炎がたちまちに渦を巻く。
ロキの姿は、気付いたら二人の視界にも見えなくなっていた。まるで、蜃気楼のように。
一体なんだったのであろうか。ミラは腰を抜かしてしまい、座り込む。
ゼウスがミラに大丈夫、と声をかけるがミラは生返事をするだけだった。
ミラの脳裏には、戦争。その二文字が浮かんでいて、途端に恐怖を覚える。
ゼウスがミラの視線に合わせ、声をかける。
ミラが落ち着くまでは、ゼウスは優しくミラのことをなだめていた。
今はそのゼウスの優しさに、ミラは受け止めているままでいることにした。
戦争は、日常のすぐ隣にまで迫ってきている。