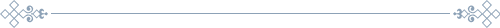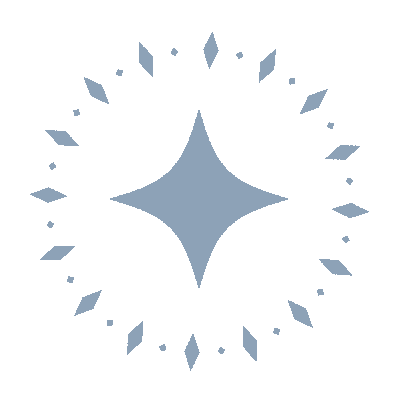Amartya tis Theos
終焉の黄昏
その瞳には、炎しか映されていない。
オーディンの閉ざされた瞳とはもう片方の、まるで黄昏を思わせるような紅い瞳。
彼は選択した。それが間違っているとも知らずに、ただそれだけを選択したのだ。
ゼウスは、その惨劇を、ただ見ているだけしかできなかった。
「……っ。どうして……どうしてそんなことをするんだッ!!」
オーディンの周りには、血の海。彼は自身が血塗られたものになっていてもどこ吹く風だった。
傍らにはロキとヘイムダル、神々達がもうぴくりとも動かないまま、横たわっている。
どうして。ゼウスの言葉はそれだけしか出てこない。
その様子にくつくつとおかしそうにオーディンは嗤った。
「どうして、と言ったな? 俺が、あいつの遺したものを護る。そのためには全部最初からこうすればよかった話までよ」
「あいつ……遺したもの?」
「──時間だ。じゃあな、仲間と共々潰れろ」
ぐしゃり。何かが潰れる音ともに現れたのは、刹那のことであった。
刹那の間、人々は見たのだろう。大樹が淡く光り輝いていたのを。
大樹の根が、意思を持ったかのように、人々を襲っていく。
その神が、ユグドラシルなんて世界の名を冠したのは、その時からであった。
何故だ。ゼウスは思考する。何故、仲間までを犠牲にした。その疑問は尽きることはなく。
やがてそれは、ゼウス達にも這いずり上がってくるのだ。
「……ッ! ポセイドンにい、さま……」
その瞳に映すは兄と慕っていた神が大樹の根によって腹を貫かれている姿であった。
瞬間に、ゼウスは考えるよりも先に、体が動いていた。駆ける、駆ける。
どうして。ゼウスの言葉はそれだけしか出てこない。
駆けていくうちにも、悲鳴は聞こえてきた。どうして、こんなことに。ゼウスも、人々も、思ったこと。
オーディンに戦争を終わらせないかとか、どうして戦争を起こしたんだとか、話すつもり、だった。
ポセイドンは倒れ、その腹にはぽっかりと大きな穴が開いていた。
亡骸となったポセイドンに、ゼウスはただただ思考が追い付かないでいたのだ。
死。目の前にあるそれは死とそれと、絶望。
人々が、神々が無惨にもユグドラシルによって命を奪われていく。
悲鳴がやけにゼウスの耳に強く残り、反響される。
守りたかったもの。しかしそれはひとりの神によって壊されてしまった。
それでは、今の自分はなんなんだ。ゼウスは思考する。
胸の鼓動がやけに騒がしいと感じさせられる。なんだか息苦しくも感じさせられた。
彼にはもう、絶望と自分に対する失望しか、残っていなかったのだ。
いつしか話した「神は人に希望を与えるものだ」と言った言葉ですらも、今は。
「……はは、なにが世界を護る、だ。託されたことも、なにひとつ護れてないじゃないか」
「僕は……主神失格だ」
渦巻くは絶望。それは確かにゼウスを変質させるものであり、そして。
ゼウスは、左目を大樹の根に貫かれたのだ。血が涙のように流れ、そして視界は狭まる。
変化。ゼウスの右目は変色していき、左目には赤い薔薇を咲かせ、もうあの頃のゼウスとは違う姿になっていく。
その時、気配がするのを感じられた。ゼウスは顔を見上げ、正体を見ようとする。
そこにはミラとよく似た少女が、立っていた。金色の目は今のゼウスと同じ輝きを持っている。
少女が、ゼウスと名前を呼んだ。
「……ミラ?」
「……私はアミール。ミラの……記憶の欠片。ミラの側面」
「帰りましょう。ゼウス。まだ、あなたは死ぬべきではない」
アミールと名乗ったミラとよく似ている少女は手を差し伸べて言うのだ。
その手を見つめてはふいと視線を逸らす。逸らせば赤い血の海が視界に映される。
記憶の、欠片と言った。それはミラと関係があるのだろうかとゼウスは思った。いいや、もしかしたら。
「……死にぞこないの僕に、そんな言葉」
「いいえ、あなたもゼウス。私が守りたかったひとよ」
アミールは真っ直ぐと、ただその瞳にゼウスだけを映して言う。
ゼウスは思う。この少女を信じていいのか。それ以上に、こんな自分でもゼウスと言ってくれるのが、少しだけ嬉しかった。
迷っていたゼウスは、恐る恐るとその手を取った。アミールはふ、と少しだけ笑う。
「私だけじゃどうしても足りないの、だから私とあなた。二人でこの最悪な結末から逃れましょう」
ぐにゃり。ゼウスの視界が歪んだと共に、死にぞこないの神とその少女は惨劇の場から姿を消したのだ。
そこには、ぽつりと薔薇が先、そして散っていった。
結局、その場にいた者達、神々はユグドラシルによって命を奪われてしまった。
ただひとり、時空へと消えていったゼウスを除いて。
シャンエリゼ。今は亡き神々達が集っていた神殿。
そこでもう帰ることのない者を待っていたミラは、惨劇を見た。
大樹が、仄かに光り呼応しているのを、そして人々達の命が奪われていくのを。
どうして、どうして。ミラは駆けていき、虚空に問いかける。どうしてだと。
道行く場所は亡骸ばかりで、ミラは泣きそうになったりなんかして。
逃げる場所なんて、もうどこにもないというのに、少女は駆けていく。
そうして辿り着いたのがゼウスが鎮座していた場所だ。ミラはずりずりと座り込んでいく、息を整える。
静寂。しかしながら魔の手はすぐそこにやってきているのだ。ズリズリと音が聞こえてくる。
ミラはネックレスをきゅっと握り、祈る。
そしてネックレスはそれに呼応するように、煌く。ちかり。その光はまるで迅雷のように。
光がミラを包み、そして。
もうこの世界に生きている人間などいない。たったひとりの神と、ふたりの少女を除いて。
惨劇とも言えようこの結末は、望まれてはいないのだ。