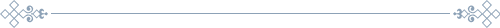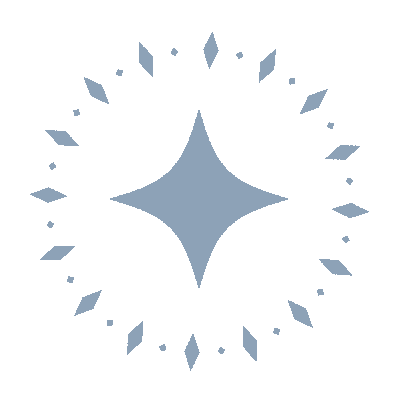Amartya tis Theos
神々よ、戦え。人々よ、逃げ惑え
貫くは閃雷のごとく。そして呻き声、鮮血に染まる世界。
この交わった世界はどうして変わってしまったのであろうか。数日前の世界を想う。
選ばれなかった未来は想像しない、はずだった。はずだったのに。
もしも、もしもだ。もし二柱の神達が和解をし、この世界達を支えてくれる未来があったとしたら。
きっとそれは、誰も傷つかない、幸せな世界なんだろうと、そう思ってしまうほどには。
あまりにも、この世界は残酷の時を刻んでいるのだ。
ああ、また駄目だった。赤に染まるのも構わずに亡骸を抱える。
守りたかったひと、優しかったひと。暖かったはずのひと。
次こそは、次こそはきっと、思い描いていた世界へと──。
まどろみから目覚める。なんだか夢を見ていた気がするが、それはも記憶に映されない。
何度目かの思い出せない夢。
ミラは夢なんかを置いて、きっと明日も朝と共に目覚めるのだ。
時刻を見れば朝の五時。まだゼウス達はいるだろうか、と部屋を出てみる。
響くドアの音が、やけに耳に響いた気がした。
しんとした静けさ。白い壁と床。それがどこまでも続いていくように思えた。
とある声が、ミラの耳に届いた。ミラはこの声をよく知っている。
視界には、見慣れた白と青。ミラはそれを視界に入れると駆け寄る。
「ゼウス様、ポセイドン様!」
「おや、ミラじゃないか。起きてしまったのかい?」
「よっ、随分と早起きだな」
ミラの声を聞くと、ゼウスは視界に入れ笑みを浮かべるのだ。ポセイドンもニッと笑う。
何をしていたか、なんて聞くのも変な話であろう。なにせ、二人は真面目な顔をしていたものなのだから。
きっと戦争のことだろうと、ミラは思いながらも二人の言葉には返事をする。
特に用事はないのだと伝えると、二人は先程までしていた話に戻ったようだ。
それを傍聴してみると、負傷者の人数や死亡者の人数まであらわになったものだから、ミラは気分を悪くさせてしまった。
そんなに被害者が出ていたものか、と現実を突きつけられる。
戦争。それも神々との間だ。人間はどうすることも出来ず、逃げ惑うだけ。
それを理解しようとしても心というものが拒んでしまうものなのだ。
ふらりとミラは逃げるようにその場を去っていった。ゼウスとポセイドンの二人は、それに気付くことはなかった。
どこまでも続くような白い床を、歩み続ける。響く足音がやけにうるさく感じる。
あてもなく歩み続ける中、ミラの視界に入る者がいた。
「おはよう、ミラ。調子はどうだ」
「ハデス様。はい、まずまずで」
視界に入ったのは、ゼウスとポセイドンの兄である神のハデスだった。
ミラの言葉を聞くと、そうか、と笑みを薄く浮かべる。
ゼウスやポセイドンのようにミラのことを気にかけてくれる神。
ゼウスと比べると話をした回数は少ないのだが、彼もまた心優しい神だと、ミラは思うのだ。
薄く浮かべられた笑みに、ふと。
「……? ハデス様、なんだかお疲れみたいですね」
「……ああ、ここのところ冥界は大忙しでな」
冥界。その言葉にミラは萎縮させる。ああ、そうか、と。
そんなミラを見て、ハデスは苦笑するのだ。
「気にするな、ミラのせいではない」
そうであっても、やはり心というものは痛むもので。
何人が、今日という明日を生きたかったのだろう。何人が、生を望みながらその生を閉ざしたのだろう。
それを考えていると、胸が苦しくなり、目の奥が熱くなる。
「……私も、今この瞬間を大事にしていきませんとね」
ぱちり。ハデスは瞬きをする。そしてすぐに寂しそうな顔をさせるのだ。
どうしてそんな顔をするのだろう、と思うのだろう。ハデスの胸の内なんて知らないままで。
そんな刹那を生きるようなことは言わなくていいんじゃないか。
願わくば、どうかそのまま生きてほしいと、ハデスは思うのだが。
時計の針も6時を示す頃。ミラはハデスと別れを済ます。
長い白の道から、外に出てみる。陽が昇る空、歌う鳥達、風に乗る雲。
何度見ても、これが戦争が行われている世界の光景だと信じられないもので。
そのまま歩みを進めていると、気付いたことがミラにはあった。
足音。それも、ミラのものではない、もうひとつの。
誰かが、ミラを追っているのだ。ミラが歩みを止めると、その足音も止む。
ミラは、振り返り、誰のかもしれない足音に向かって言う。
「……だ、誰、ですか、」
その声はやけに弱々しくこぼれ落ちていく。
それに応えるのは、見覚えがある金色の髪であった。
「おっと、助けなんて呼ばないでよ。痛い目にあいたくなかったら大人しくしてなよ」
足音の正体は、あの日確かに出会ったロキであった。
何の用だろう、と後退りをしてみせるミラと、近付くロキ。
警戒するミラのことなんかも知らないでひょいとロキはミラを抱える。
抵抗、はしようとしても、出来なかった。
誰にも知らされず、ミラはロキに攫われたのだ。
それを誰かが知る頃には、ミラは遠くの世界に行ってしまっているものなのだ。
アスガルド。北欧の神々達が住まう場所。
そこに、ミラはひとり囚われていた。
(ここ、あの大樹の中……? 本当に人が住んでいるだなんて)
そうして、ミラの目の前にいるのは、黒の髪に赤い瞳。ロキにはオーディン、と呼ばれていたか。
オーディンは、今視界にミラを入れたまま、黙っている。
沈黙。
その沈黙を破ったのは、ミラだった。
「あ、あの。私をここに連れて、何をする気なんですか」
揺蕩うワイン。それは飲むことなくただそうさせているだけ。
ことり。ワインが入ったグラスが置かれればオーディンは口を開いた。
「お前を人質として捕虜することにした。そうした方が都合が良かったからな。……ああ、安心しろ、命は奪わないでおいてやる」
人質。その言葉は脳裏に響く。都合が良い、捕虜、命。
ぐるぐると巡らせる言葉達に、ミラはオーディンの言葉に返事をすることはなかった。
やがて、恐怖が今更になって出てきたものだから、目の奥がじんわりと熱くなり、視界が歪む。
その感情を名付けるのだとしたら、恐怖。
やがてぽろぽろと泣き出したミラなんてことも知らずにオーディンはただミラを見つめる。
ただひとりの少女と、ただひとりの神の空間。
それを破られるのにはそう時間はかからなかった。
「オーディン様、お呼びでしょうか」
「ヘイムダル。お前がこの小娘の面倒を見ろ」
見慣れない青。それはヘイムダルと呼ばれる男だった。
え、と声をあげつつも、その青はミラに向けられる。
何故だか、その青い瞳は生気が感じられないものだったもので、ミラの恐怖心はますます積もるばかり。
ぽろぽろと泣く少女と、戸惑う神。
ヘイムダルは屈んでミラを宥めようとはするものの、この神は気の利いた言葉なんてものはかけられなかったのだ。
「……、と、その、いい加減泣き止んだらどうなんだ。オーディン様が困っているだろう」
別に、困ってはないのだがな、とオーディンは思うが口には出さない。そういうところが意地の悪いところでもあるのだ。
泣き止もうとしても、涙は出るばかりで、止められない。
どうしたものか、とヘイムダルは困ってしまうが、やがて身に付けていたマントでミラの涙を拭う。
そうすることで、ミラは遠慮もしないで鼻まで噛んでしまったものだから、ついオーディンは笑みをこぼしたのだ。
「あ、鼻水……オーディン様、笑っているくらいなら助けてください」
「いいや、お前だけでなんとかしろ」
くく、とこぼすオーディンは楽し気にヘイムダルとミラを見つめる。
それにヘイムダルは、ますます困ってしまうものだったのだ。
ミラがいないのに、ゼウス達も気付く頃だろう。