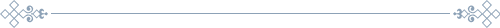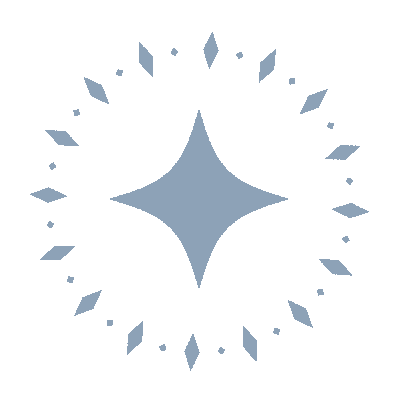Amartya tis Theos
その瞳には何を映す
ちかり。弾けるは閃雷。そして灼熱。
その光は、人によっては希望にも絶望にも成り得たものであろう。
両者の獲物が交わり、金属の音が鳴り響く。
響く音に、獣は駆け鳥は飛び立つ。
風が、戦を謳歌するかのように吹いている。
ゼウスの心には、焦り。聞けばミラは攫われたと言うではないか。
ミラを攫ったと言うのは目の前にいるオーディン、もうひとつの世界の神だ。
槍を握る手を弱めず、ゼウスは思考する。
一体、彼らは何が目的であろう、と。
ユグドラシルの異変なぞゼウスには知らざるもので、きっとオーディンの口からは明かされない。
世界が違う者同士が、その瞳の視線が交差する。
赤と、紫。まるでそれはこの新しい世界の月のよう。
赤。それはまるで世界に訪れる黄昏のよう。
「……ミラを、返してもらおうか」
「は、随分とあの小娘を気に入っているそうじゃないか」
ゼウスが、言葉で刹那の静寂を破る。それにオーディンは鼻で笑い、返す。
ちかり。迅雷が轟く。光と熱を、冷気がかき消していく。しんとした冷気が、肌をやけに痛くさせた。
ゼウスの灼熱の迅雷と、オーディンの凍てつく冷気と沈静なる水。そのどちらも引けを取らない。
「……託されたんだ。あの子のことも、そしてこの世界のことも!」
「託されたこの世界を、護らないといけないんだ!!」
閃雷が、迅雷が音を立てて弾ける。
託された、誰にだ。その疑問は“くだらない”という感情に消されていった。
くだらない、オーディンは強く感じた感情。
オーディンは、この世界が、人々が住む世界が、憎い。だからどうなろうと本当は知ったことではないのだが。
ただひとつ、言えることは。
「……そうか。俺は、お前のことが、心底嫌いだ!!」
ゼウスとオーディンでは、決して相容れない存在だということが、今此処で痛いほどわかる。
凍てつくような冷気が、周囲に広がる。それは炎すらもものともせず。
理解出来ない、ただそれだけがオーディンの心を支配していく。
愛する者を奪われた気持ちが、永遠を想った気持ちなど、一体ゼウスは理解出来るものなのだろうか。
その感情は、奪われたことのない者、失ったことのない者の感情だから成り立つものなのだと。
だから、オーディンはゼウスのことを嫌いだと、そう思ったのだ。
オーディンの放つ水は悲劇までもを流してはくれない。悲壮な感情を消してはくれない。
戦場に燃え立つ炎を、ただ機械的に消していくだけだ。
今オーディンを奮い立たせているのは、憎悪か、嫉妬か、嫌悪か。あるいは──。
その日の戦いは、決着は着くことはなかった。
当然、ミラをゼウス達に返されることも、なかったのだ。
時は廻り、アスガルド。
アスガルドの門番を任せているヘイムダルを、ミラは瞳に映していた。青が、青を映す。
ゼウス達は今頃オーディン達と戦っているのだろうか。そう考えると無性に落ち着きがなくなってしまう。
そんなミラに、大人しくしろ、なんて声をかけたりもするヘイムダル。
しかし、これではまるで、監視ではなくお守りをされているようだ。それはミラもヘイムダルも、思ったことであろう。
その実、ヘイムダルにはこんな少女を捕らえておけ、と言う方が難しい話なのだ。
さっきまでぽろぽろと泣いていた娘だ。この娘がもうひとつの世界の主神が気に入っているとはとてもではないが思えない。
一応、涙は落ち着いたようだが。今は。
「……もう涙は落ち着いたか」
「は、はい。お陰様で、あの、マント汚してしまって」
「……別に、構わない」
ヘイムダルは淡々と、それだけを返す。
しばらくしてわかったことがある。彼は与えられた仕事はやるひとなのだと。それともう一つ。
「たっだいま~、おやヘイムダル! 子守りお疲れ様だねぇ!!」
「ロキ……それはさっきも言ったことだぞ、鳥頭なのか?」
「えぇ~? 大変そ~なヘイムダルくんを労うロキ様に、そんなこと言うんだぁ~?」
彼は案外ロキに好かれている、ということだ。少なくてもミラは二人の仲は悪いようには見えなかった
喧嘩するほどなんとやら……とでも言うのであろうか。ミラはなんだか微笑ましくなって二人を見る。仲が良いのはよいことだ。
そして突如、気付いたことがある。ミラはハッとし、オーディンを待つ。
オーディンがちょうど帰ってきた。そのオーディンに駆け寄るは、一言。
「あの! ゼウス様達は、ご無事なんですよね!?」
オーディンの黄昏の目がミラを視界にとらえる。彼が今何を考えているのか、それはミラには知る由はない。
だけれども、なんだか不機嫌そうなのは目に見えてわかることだ。オーディンはゼウス、という名に眉間のシワを深くさせる。
あいつはそんなヤワじゃないことぐらい、知っているだろ。それを言い捨ててはオーディンは何処かにさっさと行ってしまった。
一体どうしたのだろうか、それも、ミラには知らざるものなのだった。
シャンエリゼ。座にてゼウスは思考していた。ミラのことである。
小さい頃に槍を教えていたことはあるが、それが今の彼女になって扱えるか。
槍だけではなく、魔法も教えるべきだったか、確かミラの適正属性は光だったはずと思考の海に駆け巡る。
それにしても、ミラは何故幼い頃の記憶がないのだろう。
ゼウスも疑問に思っていた。記憶喪失、というものなのか。
それにしてはあまりにも唐突なのもで。
大きな怪我をしたとか、成り得る理由がないのだ、ミラの記憶喪失には。
一体、どうして。
考えても考えても、その答えは導きはされなかった。
「……いいや、今はこんなことを考えている場合じゃない」
それよりも先に、ミラを人質から解放せねば、と。
今頃ミラはどうしているだろうか。怖いのだろうか、不安なのだろうか。
ひとり、敵地に攫われたミラのことを考えると胸が痛くなる。
ミラが今置かれている状況は、少女にしてはあまりにも酷すぎるのだ。
刹那、ポンとゼウスの肩に手が置かれた。ゼウスは、その手をよく知っている。
「ゼウス、ミラのことはお前のせいじゃないからな? あんまり思いつめるなよ?」
ポセイドンが心配そうに顔を覗かせていた。
ゼウスにはそれには大丈夫だよ、とは返すもの、ミラが攫われたのは自分のせいだと思っているのも事実で。
そんなゼウスを、しょうがないな、と言いたげにしてポセイドンは遠慮なくゼウスの頭を撫でる。
そんな年ではないことはわかりきっているのだが、しかし。
義兄からの労いに誰が拒めるというのだろうか。頭を撫でられたゼウスは照れくさそうに微笑んだ。
ゼウスは思う。ミラは今頃何をしているだろうか、怖い思いはしていないだろうか、と。
その思いは、夜の月に溶けては消えた。