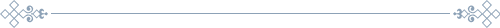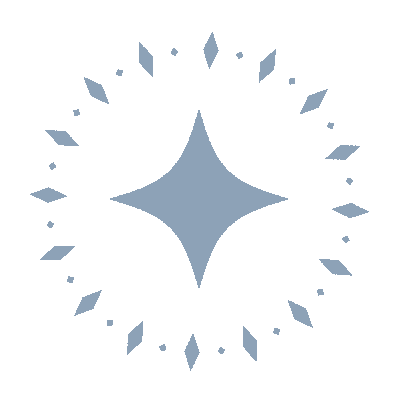Amartya tis Theos
永遠に埋まることはない空白
夢を、見た。それは刹那であり、とても幸せな夢だった。
笑っている。花のような笑みを浮かべ、あの人は手を差し伸べて。
その手は、きっと取ることは出来ないのだろう。オーディンは夢の中ながらに思っていた。
それでも、それでも手を伸ばさずにはいられない。
指先と指先。触れようとしたときには、もう──。
オーディンは目が覚める。珍しくうたた寝をしていたようで、気付けば肩に毛布がかけられている。
静けさの中、オーディンは目を凝らす。今は自分以外誰もいない。
らしくないな、と思ったことだろう。夢を見たことか、はたまたは。
オーディンは、胸に空白を感じていた。それは、オーディンの妻だったフリッグが亡くなってから、ずっとそうだ。
きっとこれまでも。そしてこれからも胸の空白は永遠に埋まることはないのだろうと、オーディンはそう思っていた。
「……フリッグ。俺はあとどれくらい、この世界を生きたらいいんだ」
それに答えられる者は、もう人間の醜さも穢れも知らないままに、彷徨うひとになってしまった。
静寂。ただそれだけが彼の言葉に答えた。
こばれるのは、深いため息。暗い部屋に、ひとり。
気分晴らしにオーディンはミラの様子を見てみることにした。部屋を出て、歩む。
歩んでいる間にも幾多の神や戦乙女とすれ違ったもので、それらはオーディンには少し眩しかった。
大切なものを亡くしていない者達。ゼウスだって、ミラだってそうだ。
それが、羨ましくて妬ましい。だから人間も嫌いだし、神だってそうだ。
ミラは、門番をしているヘイムダルと一緒にいた。
ヘイムダルとは少し打ち解けたのか、笑顔を浮かべているのがオーディンの視界に捉えさせた。
先にオーディンに気付いたのは、ミラの方であった。気付けば、軽く手を振ってみせていたのだ。
オーディンは、それに返すことはなくミラに歩み寄ってみせる。
「ヘイムダル、こいつを借りるぞ」
「えっ、ああ、はい。どうぞ……?」
ヘイムダルなんて気も止めずに、オーディンはミラの手を引く。わけもわからないミラと取り残されたヘイムダル。
オーディンは呼びかけるミラの声を無視して、歩む、歩む。
雑踏をかきわけて、やがて雑踏ではなくなる。歩みはまだ止まらない。
視界には緑が映り始め、ずいぶんと賑やかだった声達も遠くに感じさせる。
そうして、歩んだ先が森の奥、泉のほとりだった。ほとりの傍には、墓がぽつり。ひとつあった。
墓には、白い薔薇が添えられてある。まるで寄り添うかのように。
一体誰の、とミラが考えているとぽつり、ぽつりとオーディンが静かに言葉を紡ぐ。
「……フリッグ。俺の妻だった奴だ。フリッグは花が似合う奴だった」
「しかし、フリッグある日、人間共に殺された。その日から俺は胸に空白を抱えたままだ」
「お前は、永遠を想ったことはあるか」
ぱちり。ミラはその言葉に瞬きをさせた。永遠。刹那を生きる者にとっては、縁もない話だ。
思考。しかし永遠という存在を理解するには、ミラはまだ幼すぎた。
静寂。水の音が心地よく、歌うかのように聞こえてくる。
木漏れ日が、風に揺らぐ。影は二人を隠すかのように境界線と重なっている。
(……永遠、だなんて。考えたこともなかった。でも、オーディン様はなぜそれを?)
オーディンの赤の瞳はミラを映しており、ミラの青の瞳もオーディンを映している。
視線は、交わったまま。さあさあと風の声も聞こえたりなんてして。
巡っても、巡っても答えなんてものは出てこなかった。
「……お前にこんなことを話すだなんて、俺はどうかしている」
もういいぞ、なんて言葉と共にオーディンはそっぽを向いてしまう。
その横顔が、ミラにはなんだか寂しそうに見えた、気がした。
その墓が、一体誰のものなのかも、わかった気がして。
ミラは、口を閉ざしてしまう。こういう時はなんて声をかけたら正解なのだろう、と。
しかし、オーディンは慰めの言葉もいらなく、ただ問いたかっただけ。
ミラが、その答えを出したなら、何かが変われるような気がしたのだ。
ミラは、胸の内で祈ってからその場を後にする。ここには長居してはいけないような。
ひとり、残されたオーディンはただただ、目の前の墓を見つめていただけにすぎないのだ。
心は残されても、そんなことなんて知らない時は進んでいく。
「……どうしたんだ、その顔は。何かあったのか?」
戻ってきたミラを見るなり、ヘイムダルは言う。そんなに顔に出ていただろうか、と思ったことだろう。
きっとオーディンのことは言ってはならぬことだ、首を横に振るが浮べるは浮かない表情ばかり。
そんなミラを見て、ヘイムダルは少しの間、思考。
やがて何かを取り出してはミラにそれを差し出した。お菓子だ。
「何がったかは知らないが。そんな顔されたら俺も困る」
そんな不似合いな言葉なんてヘイムダルは並べてなんかしてみせた。
きょとん、とさせたあとに、ミラはくすくすと笑う。それに今度はヘイムダルがきょとんとさせて。
「何かおかしいことでも言ったか?」
「いえ、ふふ。優しいんですね」
「……ッ、いや、別に……」
照れくさそうにしてみせるヘイムダルにミラはますますくすくすと笑いをこばしてみせる。
きっとロキも、オーディンも、北欧の神だって悪いひとではないのだろう。
だからこそ、ミラは戦争なんてなくてもいいと、そう考えるのだ。
一体、何故オーディンは戦争なんか起こしたのか。
それを語られる日が、いつかくればいいと、今はただ願うだけ。
願わくば、彼の助けになって戦争なんかなくなればいいと、そう願っているのだ。